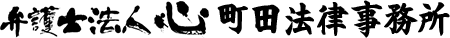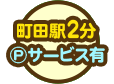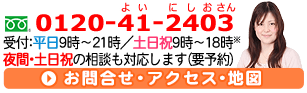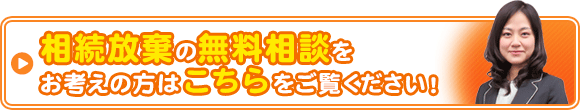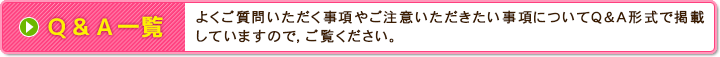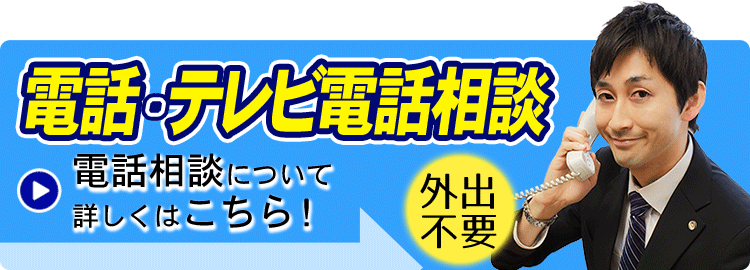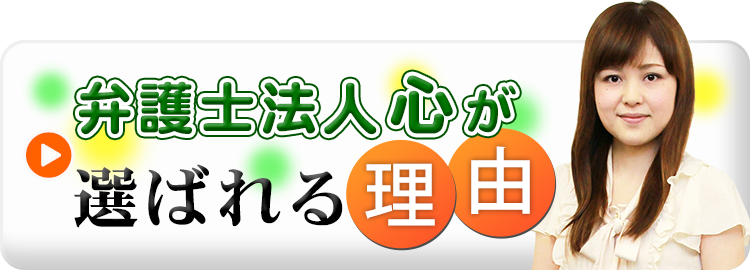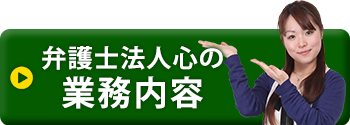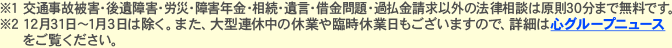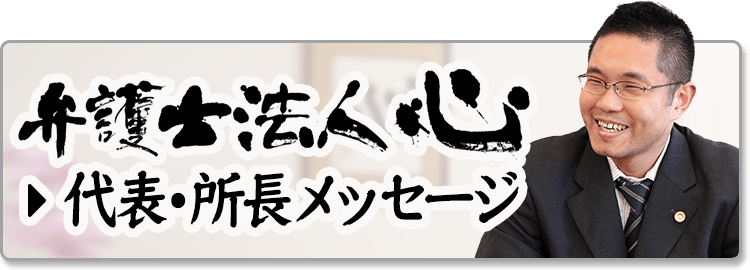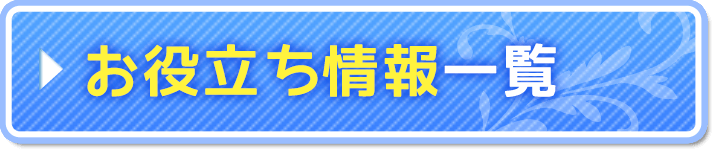生前贈与を受けた後で相続放棄をする場合の注意点
1 手続きは家庭裁判所で行うこと
相続放棄をすると、はじめから相続人ではなかったことになります。
そのため、相続財産は預貯金や不動産などのプラスの財産だけでなく、借金などのマイナスの財産も相続をしないということができます。
ただ、相続放棄の手続きは、あくまでも家庭裁判所でしか行うことができません。
単に、相続人間で相続を放棄した、自分は要らないなどと主張するだけでは、相続放棄をしたことにはなりませんので、注意が必要です。
2 生前に多額の財産の贈与を受けている場合は相続放棄が否定されることも
相続放棄は、被相続人の生前の借金まで一切相続しなくてよくなるという強力な手続きです。
ただ、被相続人に預貯金等のプラスの財産もマイナスの財産も両方ある場合、相続放棄の効果を知っている者が悪用すると、生前に多額の贈与を受けておき、いざ相続が開始すると相続放棄をして債務を免れつつプラスの財産をすべて取得するということができてしまいます。
この点について、相続放棄自体が債権者を害する行為であるとして、詐害行為取消権の対象となりうることには注意が必要です。
詐害行為取消権の対象となることが認められた場合、相続放棄が取り消され、相続人が被相続人の債務を免れることは認められないこととなります。
相続放棄の期間は、原則として、被相続人が亡くなってから3か月以内に判断することが求められることになりますので、亡くなった後に詐害行為として取り消されるか否かを悩んでいては手遅れになる可能性もあり得ます。
生前の贈与を受ける前に、被相続人に債務があることを含め、相続に詳しい弁護士に相談したうえで、適切な対策をとられることをお勧めします。